
竹富島の木造平屋民家
石垣島で住宅を建てるときに、一度は考える
鉄筋コンクリート造(RC造)か木造か
※他にもいろんな工法があるけれど
まず大きく選択肢で上がるのはこの二つでしょう。
そしてよく上がる木造住宅のイメージは
「台風に弱いのではないか」
「高温多湿で長く保たないのでは?」
など耐久性について
疑問視する声。
木造は耐久性がないのか?
耐久性には地震などに耐えることができる
耐震性なども含まれるが
今回は主に劣化について考えてみます。
先日休日に
私の生まれ育った新潟県にある
佐渡島に行ってきました。
金山などでも有名な佐渡島には
宿根木地区という
江戸時代後期から明治時代にかけて
建てられた港町の木造住宅の立ち並ぶ
集落があります。
今回はそんなお話も交えながら進めていきましょう。
佐渡の宿根木地区に行ってきました

佐渡島の南側に位置する地域で、
江戸時代から明治時代にかけて北前船の寄港地として
栄えた集落。
狭い土地に建てられた家々や石畳の路地が入り組んだ街並みは
まるでタイムスリップしたような
感覚にさせてくれる。
こちらの地域に建つ民家は
多くが築100年を超える建物で
国の重要伝統的建造物群保存地区に
指定されています。
ちなみに、竹富島も
同じく「重要伝統的建造物群保存地区」に
指定されている場所です。


築100年以上の木造住宅(外壁も材木)も
メンテナンスをされながら
長く維持されています。
さて、今日の本題です。
木造住宅の耐久性は鉄筋コンクリート造に比べて
劣るのか?について。
歴史的な上記のような事例を
基に考えると、木造住宅は
決して耐久性に劣るわけではない。
と私は考えます。
寺院などのように
築数百年も守られ続ける建物もありますし、
本州はじめ古民家は築100年以上のものも
まだ現存しているものがたくさんあります。
また今回ご紹介した
佐渡島の宿根木の民家や
竹富島の琉球古民家(もちろん石垣島にもある)
のような、海沿いの潮風の強い地域でも
100年以上の月日を経て
今もしっかりと人々の暮らしを支え
外から来る方の観光名所としても
活躍し続けているのです。
木造住宅が朽ちる理由
では木造住宅の中でも
なぜ朽ちる物件があるのでしょうか?
それにはいくつかの理由があります。
・菌による腐朽
腐朽菌と呼ばれる菌により木材が腐る
・外部からの侵食
シロアリなどにより木材を餌にされる
などです。
そしてなぜ菌やシロアリに
木材がやられるかと言うと・・・
特に<水分>が原因になりやすいと考えています。
※詳細はこちらの記事では省きます。
水分を減らすには
・乾燥材を使うこと
そして、
・水分が木材に供給される状況を
抑えることが大切。
これは雨漏りなどもそうですが
建物の内部で土台、柱や梁がある部分に
湿度や実際の水分が溜まり続けるような
状況を防ぐことがとても大事になります。
この他にも材木の種類や材木のどの部分を
使うかによっても耐久性は大きく変わります。
本州であればヒノキやヒバ
沖縄の木も
リュウキュウマツやイヌマキなど
があります。
家づくりは奥が深い
湿度が溜まる原因は
雨漏りなどのわかりやすい理由だけじゃない。
壁体内結露のように
壁の外と内の温度差で結露が発生する場合も。
壁体内結露は多くの場合は寒冷地で
冬の温度差で起きることが多いです。
ただし高温多湿の石垣で
エアコンの使用時間も長くなっていることも含め
結露や内部の高温多湿による
菌の発生にも注意が必要。
建物はしっかりと信頼のおける
建築士、施工会社に相談しましょう。
不動産だけじゃなく、建物、そこからの暮らしについてまずはご相談ください
元々新潟県の住宅会社で働いていた経験を活かし
信頼できる建築士さんや施工会社さんを
ご紹介・お繋ぎします。
また現在はリノベーションのデザインなどもに
関わらせて頂いているので
ぜひ土地や建物に関して・・・
どんな場所で、どんな風に
暮らし方や生き方をしていきたいか?
まずはお気軽にご相談ください。
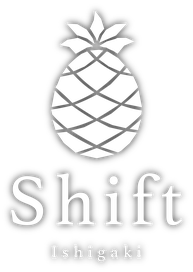

コメントをお書きください